ビジョンの浸透と実現をめざし、地道に取り組み続けていきたい。(広報課長 高濱悠紀さん)
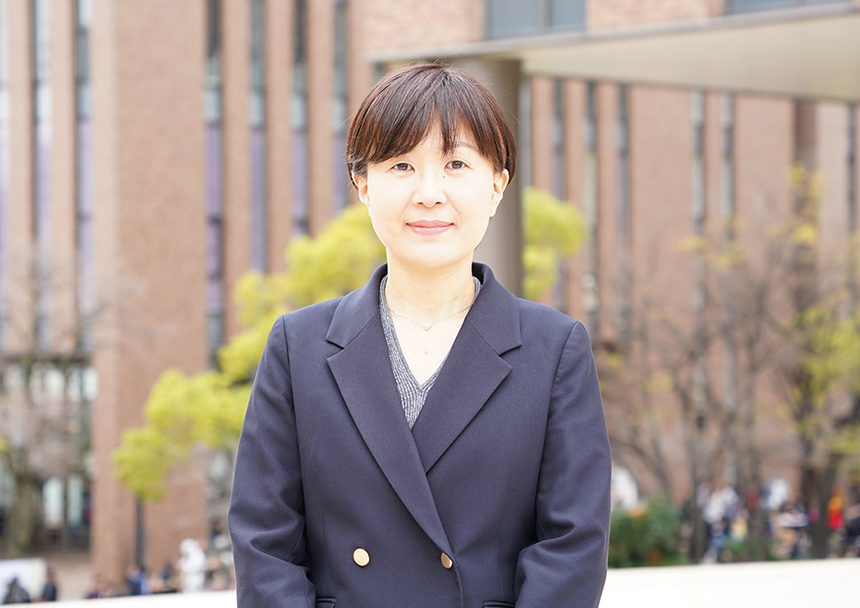
ビジョンの実現に向けて取り組みを進めている職員へのインタビューです。ビジョンを推進していくための職務内容や、2032年に向けての抱負を語ります。
※肩書はインタビュー当時のものです。
大学運営・組織ビジョン
居心地の良い学びの場を形成する
空間・制度の面から、学びを誘発するキャンパスをデザイン。
教職員の能力を発揮できる組織運営を行い、ビジョン実現の土台を形作ります。
広報は、人と想いに光をあてる仕事
通信関連企業を経て、2004年10月に入職しました。最初の配属先である学務課には5年ほど在籍し、主に研究支援に携わりました。次に配属されたのは総務課です。約10年在籍し、周年事業のほか、同窓会や在学生の保護者で組織する後援会、地域の方に対応する業務を担当しました。その後、2019年に広報課に異動になり、現在に至ります。広報課の主な業務は、ブランディング、大学ホームページやパンフレットをはじめとしたオウンドメディアの企画・制作・運営、広告の出稿、報道機関対応など。本学の創立70周年記念事業の一つとして生まれ、今年で第25回を迎える全国高校生エッセイコンテスト「17歳からのメッセージ」 も、広報課が運営しています。
異動して間もない頃、広報の仕事は人前に出るイメージがあったので、どちらかと言えば苦手意識を感じていました。しかし、実際に仕事を積み重ねていく中で、自分たちがキラキラするのではなく、何かに取り組みがんばっている人たち(本学では学生や教職員)を見つけて、光を当てることが広報の役割なのだとわかってきて、今では人を輝かせることができるすばらしい仕事だと感じています。
私が広報の仕事の中で、最もおもしろいと感じているのが取材です。本学では、ホームページを中心とした情報発信を行っており、取材を起点にコンテンツをつくるスタイルを大切にしています。取材では、教職員や学生へのインタビューを通して、たくさんの学びや気づきがあります。また、「話を聞いてもらっているうちに、自分の考えが整理され、新たな発見があった。取材を受けてよかった」といった声をいただくこともあり、そんなときは「いい仕事ができたかな」と、充実した気持ちになります。加えて、意識して取り入れている対談や座談会形式の取材では、創発が生まれる場づくりに関わることができているように感じています。

自分の人生のテーマでもある「創発」
総務課に在籍していた頃、本学の100周年に向けたグランドデザインを考えるワーキンググループに一員として参加しました。そして広報課に移ってからは、100周年ビジョン「DAIKEI 2032」の浸透と実現をめざすインナーブランディング事業に携わってきました。そのため、学内の誰よりも「DAIKEI 2032」の実現について考え続けてきたのではないかと自負しています。
大阪経済大学が掲げる「創発」という、一般にはあまり聞きなれない言葉をどう表現できるか。そんなことを考えながら、日々の取材の中で創発を感じる場面や言葉に出会うたびに、ノートに書き留めるようにしています。そのノートを眺めているときに、ふと気がつきました。学生時代から私の心を動かしてきたものが、まさしく創発だったのです。私は誰かと対話や議論したりする中で、自分一人ではたどり着けなかったような考えやアイデアが生まれる瞬間が、何より楽しいと感じます。だから、自分が心から共感できる仕事に巡りあえてラッキーだなと思います。
「DAIKEI 2032」にある「生き続ける学び」というキーワードも、自分自身がとても共感できる言葉です。人生における学びは、時代に応じて変わっていくし、自分の年齢や体力、家族構成などによっても変わっていきます。でも、この世界には自分が知らないことが常にあるので、学ぶことだらけであることは変わりません。だから、学ぶことが好きな私はこれからもずっと何かを学び続けるだろうし、私にとっての「生き続ける学び」は人生を通じての楽しみだと思っています。
「生き続ける学び」がより求められる社会へ
近年、急速に進化している生成AIをはじめ、技術革新のスピードはますます速くなっています。本学が100周年を迎える2032年には、誰もが常に学んでいることが当たり前になり、「生き続ける学び」がより重視される社会になっていると思います。現在の大学は、中学校や高校の延長線上にある教育機関という位置づけで、主に18歳の人たちが入学してきます。しかしこれからの大学は、常に新しい研究が揃っている刺激的な場所、本質的な学びに向き合える場所として、多種多様な人々が集うようになっていくのではないでしょうか。幅広い世代の人たちが共に学び、それぞれの立場から喧々諤々意見を交わして、さまざまな価値観が行き交う、まさしく創発の場になっていけばと願っています。

私は昨年、他大学で開講された文部科学省BPプログラムを1年間受講し、私学経営について学びました。一緒に受講していた人たちは大学の教員や職員、理事、私立中高の校長や教諭、一般企業の社員や定年退職者など、立場も年齢も業界もばらばら。それでも、グループディスカッションではみんながフラットな目線で意見を交わし合っていました。多様な知見や経験、価値観が重なったりぶつかったりしながら創発が起こるのを目の当たりにし、これからの大学がめざすべき姿を自ら体感できたのは、貴重な経験だったと思います。
2032年には、「創発」「生き続ける学び」というキーワードが、教職員の会話の中に当たり前のように存在している状態を実現できればと考えています。さらに学生の皆さんも、もし「創発」という言葉を知らなくても、説明すれば「そういうことか。それなら大学で経験したことがあるな」と腑に落ちるような状況になっていれば理想的だと思います。今後も「DAIKEI 2032」の実現に向けて、自らの役割を果たしていきたいと思います。
Hints for SOUHATSU
創発につながるヒント
「話を聞くことの大切さに改めて気づいたのは、人生における新たな発見でした。取材は一生を通じて続けていきたいです」と語ってくれた高濱さん。教職員から「取材を受けて良かった」と感謝の言葉をかけてもらうことも多いそうです。インタビューや対談、座談会などは、創発を生み出す一つの手段として非常に有効だと言えるのではないでしょうか。また、本を読む、講座を受講するなど、常にインプットをしながら新たな業務に挑戦している高濱さんの姿から、教職員の一人ひとりが「生き続ける学び」を自ら実践していくことの大切さを感じました。
理解・納得した



